認知症予防のためにも実践したい! 脳梗塞を防ぐための、冬の生活の知恵と工夫
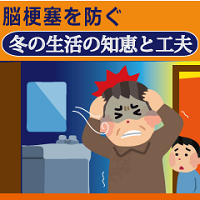
毎年1月20日は「血栓予防の日」。さらに、この日から1ヵ月間は「血栓予防月間」に制定されています。これは血栓が詰まることで生じる脳梗塞や心筋梗塞で亡くなる人が、1月に多いことを受けたものです。
ところで、なぜ血管は冬に詰まりやすいのでしょうか。理由は、冬は寒暖の差が激しく、血管に与える負担が大きくなることにあります。気温が急激に下がると、血管が収縮し血圧が上昇します。そうなると血管が破れ、脳出血を引き起こす危険性が高まってしまいます。また、気温が低い状態が続くと、血管が縮んだ状態が持続するため、血流が悪くなり脳梗塞が生じやすくなります。
脳梗塞は高齢者に多い病気のひとつですが、一命を取り留めても麻痺や言語障がいなどの後遺症が現れ、日常生活に支障をきたしてしまいます。実際、脳梗塞が原因で要介護認定を受けたという高齢者は少なくありません。加えて、脳梗塞は認知症の原因にもなります。脳の血管が詰まることで徐々に脳の機能が低下する脳血管性認知症は、認知症患者の約20%を占めています。そうした事態に至らないためには、血栓ができないよう日頃から予防に努めることが大切です。今回は脳梗塞を防ぐための冬の生活の工夫についてご紹介します。
その1:冬のお風呂場には危険がいっぱい!
 高齢者にとって最も注意が必要な場所がお風呂場。毎年冬には多くの高齢者が入浴中に亡くなっています。その原因として挙げられるのが、浴室や脱衣所の寒さ。暖かい部屋から寒いお風呂場に移動すると、血管が縮み血圧が上昇。その後、熱いお湯につかると今度は血管が広がり、急に血圧が下がります。こうした血圧の変動が心臓などへの負担となり、心筋梗塞や脳出血、脳梗塞に起因する溺死を招いているのです。
高齢者にとって最も注意が必要な場所がお風呂場。毎年冬には多くの高齢者が入浴中に亡くなっています。その原因として挙げられるのが、浴室や脱衣所の寒さ。暖かい部屋から寒いお風呂場に移動すると、血管が縮み血圧が上昇。その後、熱いお湯につかると今度は血管が広がり、急に血圧が下がります。こうした血圧の変動が心臓などへの負担となり、心筋梗塞や脳出血、脳梗塞に起因する溺死を招いているのです。
熱すぎるお湯の温度も脳梗塞の原因です。熱いお湯に入浴すると血小板の働きが活発になるため、血栓が発生しやすくなるそうです。また、熱いお湯につかると大量の汗をかくので、血液中の水分が減り、血液の粘度も高まります。お湯の温度は42℃が適温。入浴後の水分補給も必ず行いましょう。
◆安全な入浴のために……入浴前のここがPoint!
・入浴前には脱衣所を暖房器具で暖めましょう。
・シャワー、かかり湯などでお湯に体を慣らしてから湯船につかりましょう。
・入浴後はもちろん、入浴前にもコップ1杯の水を飲みましょう。
・飲酒後の入浴は危険! お酒を飲んだら最低でも1時間は入浴を避けましょう。
・高齢者が入浴する時間帯は、夕方早めがベターです。
その2:「目覚めの一杯、寝る前の一杯」を習慣に
体内の水分が不足すると、脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めてしまいます。予防のためには、こまめに水分を摂ることが大切。厚生労働省でも「健康のため水を飲もう」という運動を推進しており、特に中高年に対しては「目覚めの一杯、寝る前の一杯」を奨励しています。
夜中にトイレに行くのが嫌だから…と、寝る前に水分を控える方も少なくないかもしれません。ただ、これが脳梗塞の引き金にもなっています。実際、心筋梗塞や脳梗塞が起こる時間帯は、夜中から早朝にかけてが一番多いのだとか。高齢になると、ただでさえ喉の渇きを感じにくくなるため、意識的に水分を摂る習慣を身につけたいものです。
とはいえ、夜中のトイレは転倒事故につながる危険性あります。トイレまでの道のりに足元灯を設置したり、トイレとお部屋との温度差が生じないよう暖房器具を用意するといった配慮もお忘れなく。
その3: 部屋全体を暖かく。寒い場所を作らない
脳梗塞の予防には、血圧を安定させることが極めて重要です。ある調査では、こたつやホットカーペットのみを使用している高齢者に比べ、部屋全体が暖まっているなかで生活している高齢者のほうが、血圧が安定しやすいという結果が得られたそうです。それには暖房器具などで部屋を暖めるのはもちろん、熱を逃がさないような工夫も必要。特に気密性の低い木造家屋にお住まいの場合は、隙間テープや断熱シートを利用するなど対策を講じましょう。暖房時にカーテンを閉めることでも、断熱効果が高まります。

高齢者にとって、冬はさまざまな危険が潜む季節です。脳梗塞を防ぐという目線からも、暖かい空間づくりをはじめとした予防策に努めて、この冬をぜひ健やかにお過ごしください。
◆厚生労働省の「健康のため水を飲もう」推進運動についてはこちらをご覧ください
