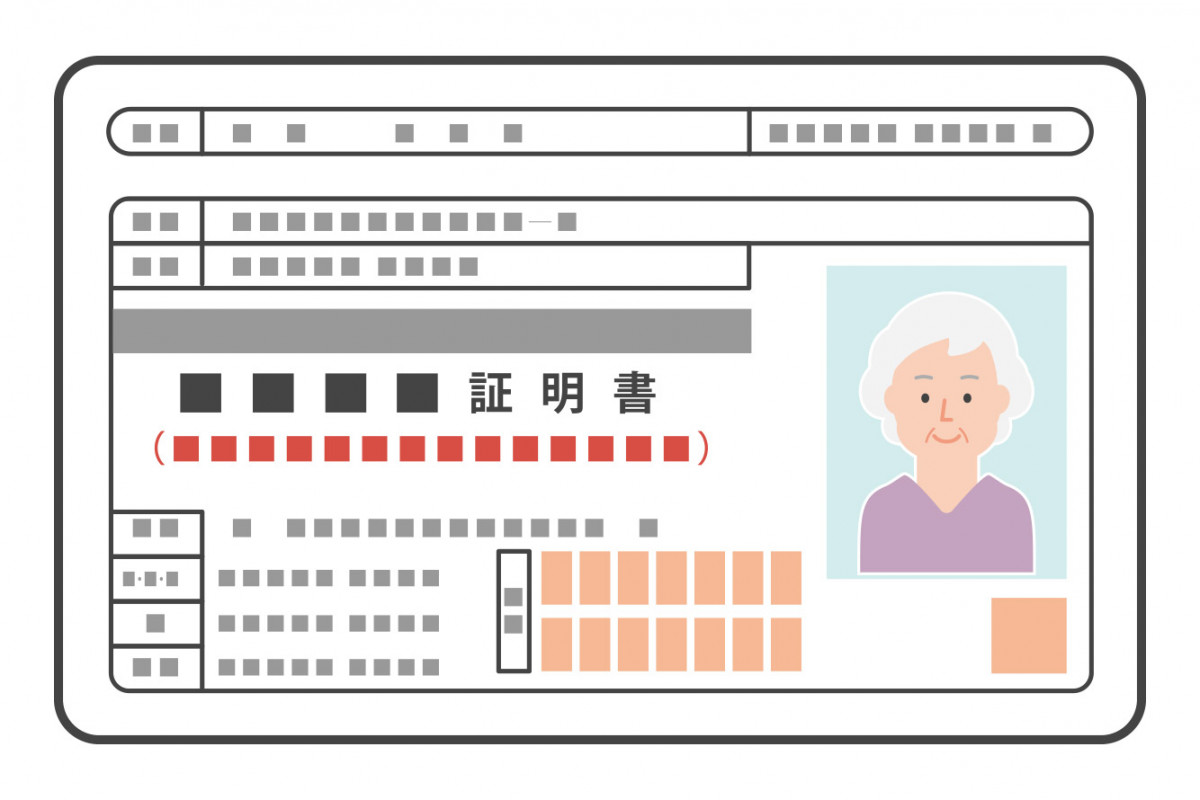親の免許返納、どうすべき?高齢者の運転リスクと認知症の関係を解説
テレビや新聞などで、高齢ドライバーの事故に触れるたび、「うちの親は大丈夫だろうか」と心配になる方は多いのではないでしょうか。どんなに元気そうに見えても、これまで通りの安全運転ができるか不安ですよね。
この記事では、親御さんの運転免許を返納させるべきか悩む方に向けて、免許返納の必要性や認知症の関係について解説します。親御さんを説得する方法についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
なぜ、免許返納を考えるべきなのか
高齢者の運転は、本当に危険なのでしょうか?まずは、高齢者の運転におけるリスクを正しく把握し、免許返納すべきかを考えていきましょう。
高齢ドライバーは重大な事故を起こしやすい?
運転免許保有者数や運転距離などを考慮すると、高齢ドライバーの事故率が特別高いというわけではありませんが、ほかの年代よりも重大な事故を起こしやすいというデータがあります。これらのデータから、高齢ドライバーは重大な事故を引き起こすリスクが高いといえるでしょう。
- 75歳以上の運転者による死亡事故件数は、75歳未満の運転者と比較して約2倍
※運転免許保有者数10万人あたりで比較した場合 - 高速道路における逆走事故の約7割は65歳以上の運転者
高齢ドライバーが重大な事故を起こしやすい理由
では、なぜ高齢ドライバーは重大な事故を起こしやすいと言われているのでしょうか。内閣府や警察庁の交通死亡事故の資料から推察できる主な理由は、以下のとおりです。
- 視力や聴力が弱まることで、周囲の状況を得にくい
- 反射神経が鈍くなり、とっさの判断や操作が遅れる
- 体力や筋力の低下により、運転操作が不正確になる
- 運転が自分本位になり、交通環境を客観的に把握できない
- 危険予測や状況判断が適切に行えない
内閣府が公表している交通安全白書によれば、ハンドルなどの操作ミスに起因する死亡事故の発生率は、65歳以上の運転者は65歳未満の運転者と比較して、5.25〜20.5倍と大幅に高くなっています。
【年齢層別】ブレーキとアクセルの踏み間違いによる死亡事故の割合
| 65歳未満 | 0.4% |
|---|---|
| 65~69歳 | 2.1% |
| 70~74歳 | 4.0% |
| 75~79歳 | 4.8% |
| 80~84歳 | 8.2% |
| 85歳以上 | 7.1% |
出典:高齢者の交通事故の状況,P30より作成
身体機能や認知機能、判断力や注意力の低下など、さまざまな要因が複合的に作用することで、高齢ドライバーの運転操作ミスが増加し、重大な交通事故につながるリスクが高まるといえそうです。
認知症と運転免許について|見過ごせないリスク
「認知症と診断されても、車の運転を続けていいのだろうか」と、多くの方が不安に感じると思います。ここでは、認知症の方の運転免許や認知症の疑いがある場合の運転について、詳しく解説します。
認知症と診断されたら、運転免許は取り消される?
認知症と診断されたら、運転を控える必要があります。認知症が進行すると、安全運転が難しくなるからです。
道路交通法では、認知症と診断された人は運転免許の停止または取り消しの対象と規定されています。また、75歳以上のドライバーは免許更新時、認知機能検査等を受けることが必須となり、検査で「認知症のおそれ」との判定が出た場合は医師の診断が義務付けられています。
認知症の疑いがある人は要注意
「軽度の認知機能低下がある」という検査結果の場合では、6ヶ月後に再検査となりますが、運転免許が取り消されることはありません。ですが、認知機能の低下は運転能力に悪影響を及ぼす恐れがあるため、やはり運転は控えましょう。
75歳以上のドライバーにおいて、運転中に信号無視等の特定の交通違反をした場合には、臨時に認知機能検査が行われます。
特に、初期の認知症は、ご本人も周囲も症状に気づきにくいことがあります。以下のような症状がみられる場合は、注意が必要です。
- 車のキーや免許証などを探し回ることが頻繁にある
- 今までできていたカーナビやカーステレオの操作ができなくなった
- 曲がる際にウインカーを出し忘れることがある
- 車間距離を一定に保つことが苦手になった
- アクセルとブレーキを間違えることがある
- 周囲から運転が荒くなったと指摘されるようになった
これらの症状がみられる場合は、早めに専門医の診察を受けましょう。
また、これらの症状により安全運転に不安がある場合は、ご本人またはご家族から、運転免許センターや警察署にある安全運転相談窓口に相談しましょう。
認知症の人が運転するリスク
認知症の人が運転を続けると、以下のようなリスクが考えられます。
- 交通事故を起こすリスクが高くなる
- 運転中に行方不明になる可能性がある
- 事故を起こした場合、家族に賠償責任が生じる恐れがある
認知症の人と家族の会の実態調査報告書によると、認知症で行方不明や交通事故を経験した人のうち、約3割が車で移動していたとされています。行方不明時に車で移動されている場合は発見が遅れる可能性もあり、とても危険です。
また、認知症の方が運転中に事故を起こした場合、ご家族が責任を問われ、損害賠償しなければならないケースもあります。
親の免許返納はどうするべきか?親を説得する方法
運転免許の返納は、親御さんの生活に大きな影響を与える決断です。そのため、頭ごなしに反対したり、無理強いしたりすることはやめましょう。
ここでは、親御さんに運転免許の返納を納得してもらうための説得方法をご紹介します。
①高齢ドライバーの交通事故の現状を話す
高齢ドライバーの交通事故の現状について、ニュースや新聞の記事を使って、具体的に伝えましょう。実際の事故の話だと、親御さんも自分のこととして考えやすくなります。
このときに、「お父さんは大丈夫だと思うけれど、最近はこのような事故が多いから心配で…」というように、親御さんを心配する気持ちを正直に伝えることがポイントです。
ただし、過度に不安をあおったり、「お父さんは運転が下手になったから」などと親御さんの自尊心を傷つけるような言い方は避けましょう。
②なぜ返納したくないのか、親の気持ちを理解する
免許返納の話をするときは、親御さんの気持ちに寄り添うことが大切です。「運転は上手だけど、耳が遠くなってきているから心配」「運転をやめるのは勇気がいるよね」と共感し、返納をためらう理由を丁寧に聞き取りましょう。考えられる理由としては、たとえば以下のようなものが挙げられます。
- 車がないと日常生活が不便になる
- ドライブが趣味(楽しみ)である
- 運転が自分の役割であると考えている
返納を嫌がる気持ちに共感を示しつつ、デメリットを解消できるような代替案を提案するといいですね。
| 返納をためらう理由 | 代替案の例 |
|---|---|
| 車がないと日常生活が不便 | 代わりとなる手段を提供して慣れてもらう
|
| ドライブが趣味(楽しみ) | 親御さんを誘導して、ドライブに代わる楽しみを見つける
|
| 運転が自分の役割 | 運転以外の役割を与える
|
③返納後のメリットを説明する
免許返納のメリットを具体的に説明するのも効果的です。免許返納のメリットはたくさんあります。
免許返納のメリット
- 運転事故の加害者にならずにすむ
- 親御さん自身の安全を確保できる
- 車の維持費が不要になり、経済的な負担が軽減される
- 免許返納者向けの特典やサービスが利用できる
メリットを理解すると、免許返納に対して前向きな気持ちになることが期待されます。
免許返納者向けの特典やサービスについては、次章でご紹介します。
④ほかの人から説得してもらう
家族で話しても説得が難しい場合は、第三者の力を借りましょう。感情的にならず、話が進みやすいからです。かかりつけの先生に健康状態を説明してもらったり、免許返納した経験者に話を聞いたりするのもいいでしょう。
免許返納後に申請すると「運転経歴証明書」が交付される
| 公共交通機関の割引 |
|
|---|---|
| 商業施設の割引 |
|
| 金融機関の特典 |
|
出典:高齢者運転免許自主返納サポート協議会加盟企業・団体の特典一覧より作成
特典を受けるためには、期限内に申請が必要な場合があるので、ご注意ください。
なお、2025年3月24日より、マイナンバーカードと運転経歴証明書の一体化が開始されました。
これにより、これまでは運転経歴証明書の提示、もしくはマイナンバーカードと運転経歴証明書交付済シールがあれば運転経歴証明書の提示と同様の特典を受けることができましたが、今後は、「マイナ運転経歴証明書」としてマイナンバーカードのみ提示すれば特典を受けることができるようになりました。
※運転経歴証明書交付済シールの交付は2025年3月24日以降中止されます。
※「マイナ運転経歴証明書」の申請が必要です。
※「マイナ運転経歴証明書」の提示には「マイナ免許証読み取りアプリ」が必要です。
免許返納後の生活で気をつけたいこと
運転免許を返納すると、高齢者の生活にとっては、移動手段だけでなく生活習慣や心理面にも影響が出ます。ここでは、返納後の生活で注意すべき点と対策について、簡潔にご紹介します。
運動不足になりやすい
免許を返納すると、外出頻度が減り、運動不足になりやすいです。運動不足を防ぐには、以下の対策を行いましょう。
- 交通機関や徒歩で、積極的に外出をする
- 地域活動や高齢者向け運動教室などに参加する
- 散歩を日課にする
- ラジオ体操やストレッチなど、室内でできる簡単な運動を行う
認知機能が低下する可能性がある
運転による脳の刺激が減ることで、認知機能が低下する可能性があります。認知機能の低下を防ぐには、運転以外で認知機能を刺激できる以下の対策を行いましょう。
- ボランティア活動に参加し、役割を持つ
- 地域や趣味の集まりに参加し、社会とのつながりを維持する
- パズルや計算問題など、脳を活性化させる脳トレを習慣化する
マイナスな気持ちになりやすい(孤独感・喪失感・自己肯定感の低下)
運転をやめたことで、孤独感や喪失感、自己肯定感の低下など、マイナスな気持ちになる人もいます。心理面の影響への対策は、以下を試してみましょう。
- 家族や友人と交流し、孤独感を解消する
- 新しい趣味や活動を見つけ、生活に変化や刺激を与える
- 免許返納の特典を利用し、外出機会を増やす
免許を返納すると認知症は進行する?
免許の返納によって、認知症が進行するという医学的根拠はありません。運転が認知機能の維持に役立つという意見もありますが、高齢ドライバーは重大な事故を起こしやすいというデータからもわかるとおり、高齢ドライバーが運転を続けることは事故のリスクを高めます。
認知症の疑いがある状態での運転は、親御さんだけでなく、周りの人も危険です。認知機能の維持は、脳トレや散歩など、安全な方法で行いましょう。
認知症予防については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せて参考にしてください。
まとめ
運転免許の返納は、「運転ができなくなる」「生活が困る」というマイナスの選択肢ではありません。むしろ、「本人や家族が、安全な生活を送るための賢い選択」とも言えるのではないでしょうか。いつまでも健康で安心して暮らすために、運転免許の返納についてご家族で話し合ってみましょう。