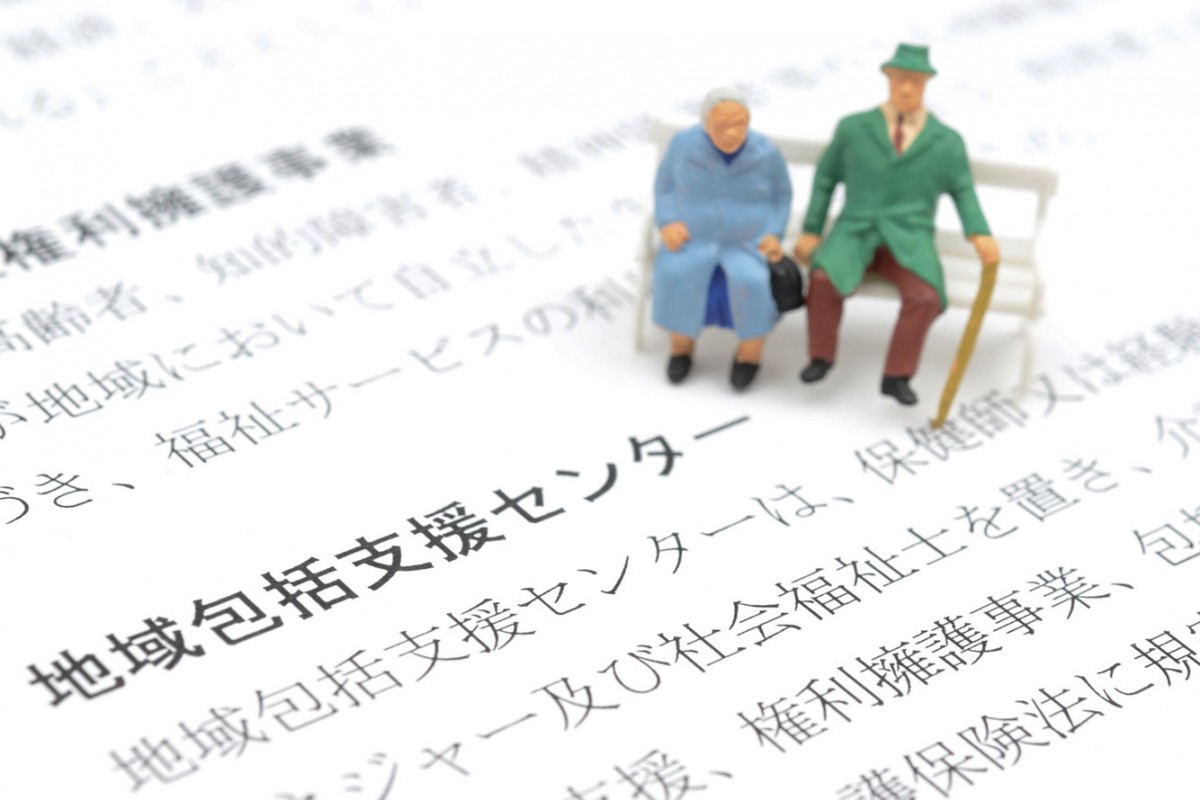高齢者の徘徊対策に!GPS見守りの活用法と安心できる備え
高齢のご家族に関して、不安に感じることのひとつが「徘徊」ではないでしょうか。認知症と診断された場合はもちろん、診断には至っていない場合や軽度の段階でも、思いがけず外に出て行ってしまうことがあります。
この記事では、徘徊のリスクに備えるための具体的な予防策から、GPS機器を活用した見守り方法、そして地域で利用できる支援サービスまで、わかりやすくお伝えします。
認知症の進行とともに増える「徘徊」の不安
徘徊は認知症の進行により必ず生じるものではなく、身体的要因や環境要因が関与することもあります。
徘徊が起こる主な原因
- 時間や場所の感覚が混乱する
- 昔住んでいた場所に帰ろうとする
- 不安や焦燥感から落ち着ける場所を探す
- 何かを探しに出かけたつもりになる
ご本人にとっては目的を持った外出のつもりでも、記憶の混乱により道に迷ってしまったり、不安な気持ちから家を出てしまったりすることがあります。いずれにしても、行方不明や事故のリスクもあるため、早めの備えをしておくことが大切です。
すぐにはじめられる徘徊への備え
徘徊を完全に防ぐことは難しくても、リスクを減らし、万が一の際に早期発見につながる工夫はたくさんあります。
1.外出に気づくための環境づくり
玄関や門扉にチャイムを設置
人感センサー付きのチャイムなら、夜間でも音で外出に気づけます。
履物を決まった場所に置く
ご本人の靴だけを出しておくと、靴がないことで外出に気づけます。
2.身元確認に役立つ準備
衣類のポケットに連絡先メモを常備
名前や住所、家族の連絡先を防水ケースに入れ、よく着る服のポケットに入れておきます。複数の服に用意しておくと、より安心できます。
衣類や持ち物への名前の記載
目立たない場所に油性ペンで記入しておきます。できれば、日頃からよく使っているポーチ、バッグ、杖などにも名前をつけておくとよいでしょう。フルネームが書いてあると逆に氏名を知られるのが不安という場合には、自治体などが発行している「見守りシール」を活用するのもおすすめです。
自治体などが配布する「見守りシール」は、認知症の高齢者や子どもなどの安全を守るため、QRコードなどで本人情報に連絡できる識別シール。衣服や持ち物に貼ることで、行方不明時の早期発見・保護に役立ちます。
3.地域とのつながり作り
近隣住民への情報共有
現在の状況を簡単に説明し、例えばひとりで歩いているのを見かけたら声をかけてもらうなどお願いしてみましょう。地域のコミュニティに理解していただけると安心です。
よく行く場所の店舗への挨拶
コンビニや商店などに事情を伝え、可能な範囲での協力をお願いします。
散歩コースの確認
日頃よく歩くルートを把握し、探す際の手がかりにします。
その他、もしもの捜索に備えたリスト作成を用意しておくとよいでしょう。
昔住んでいた家や職場など行きそうな場所の一覧や、好きだった活動や趣味の場所、移動するさいによく利用する駅やバス停、タクシー会社の連絡先などを一目でわかるようなリストにしておきましょう。
これらの工夫により、徘徊のリスクを減らし、万が一の際の早期発見につなげることができます。しかし、より確実な見守りのためには、GPS機器の活用も検討されることをおすすめします。
高齢者を見守るGPS機器・アイテムの種類と特徴
GPSとは、人工衛星からの信号を使って現在地を把握できる仕組みです。ご本人の性格や生活習慣に合わせて選ぶことで自然に見守りに取り入れることができます。
1.靴に取り付ける GPS機器
靴の中に装着するため、身につけることを忘れる心配がほとんどありません。インソールタイプや中敷きの下に設置するなど、GPSをつけていることがご本人にはわかりづらいため、気になって取り外してしまうことを防ぐことができます。
特徴
靴の中敷きや靴底に装着する小型のGPS機器
使い方のコツ
玄関に、対象の1足のみを出しておくようにしましょう。家族の靴は片付ける習慣をつけ、玄関には「履ける靴」1足を出しておくようにしましょう。また、思いがけず違う靴を履いてしまうことも考えられますので、衣服につけるタイプの機器や見守りシールなどと併用するとより安心です。
こんな方に向いています
- 物をよく置き忘れる方
- 新しい物を身につけるのを嫌がる方
- 上着やカギを持たずに外出してしまう方
- 外出の意識がないまま、パジャマ姿などで出てしまうことがある方
2.タグや薄型 GPS機器
タグ型GPS機器は衣類や手提げなど様々なものに装着しやすいサイズ感や、身につけていても気にならない軽量さが特徴的です。充電不要や生活防水など管理の手間も軽減されているアイテムもあります。小さな袋に入れて「お守り」として渡すと喜んで身につけてくれることも。
特徴
小型で軽量。工夫次第でさまざまな装着方法ができる
使い方のコツ
キーホルダー型であれば、財布やバッグなどご本人がいつも持ち歩く物につけるのがおすすめです。杖に飾りとしてや、お守りのように身につけるのも良い方法です。
薄型タイプは洋服のポケット裏や裾につけられます。アクセサリー型やストラップ型もあり、日頃からよく身につけているもの、習慣として持ち歩いているものにつけるのがコツです。
こんな方に向いています
- スマホなどが操作しづらい、できない方
- 鍵やお財布を持ち歩く習慣がある方
- GPSを持ちたくない、持たされたくないと嫌がる方
3.腕時計型 GPS機器
時計として自然に使えるため、違和感なく身につけてもらえます。中には歩数計機能付きのものもあります。家族や孫が似たようなスマートウォッチを使っているのを見せたりすると、比較的スムーズに装着してくれるようです。
特徴
見守り用というイメージが薄く、普通の腕時計として使用することができる
使い方のコツ
見守りのためのGPS機能だけでなく、日々の健康管理に役立つ機能がある機器もあります。時計型のように身につける・外すという動作が必要なアイテムです。また定期的に充電が必要になりますので日々のチェックとサポートも必要です。
こんな方に向いています
- 腕時計をする習慣がある方
- 比較的新しい物に抵抗感がない方
- 定期的な充電などをご本人でできる、またはサポートできる家族がいる
4.スマートフォン型・専用端末型
GPS機能に加え家族と通話ができるため、ご本人にも「困ったときに電話できる」という安心感があります。
特徴
簡単操作の専用端末やシニア向けスマートフォン
使い方のコツ
充電を忘れがちなので、ご家族が気にかけてあげましょう。また、家族が日常的にスマートフォンを使い「持っていて当たり前」という雰囲気をつくることで、ご本人も自然と受け入れやすくなります。「スマートフォンがあるといつでも連絡できて便利」といった会話を日ごろからするのも効果的です。
こんな方に向いています
- 電話を使う習慣がある方
- 家族との連絡を取りたがる方
- スマートフォンなどの簡単な操作ができる方
高齢者向けGPS導入時の心構えとコツ
GPS機器は、安心につながる心強い道具です。ただし、ご本人が抵抗なく使えるようにするには、使い始める際に少し工夫が必要です。自然に受け入れてもらうためには、家族の関わり方が大切になります。
成功のポイント
- 「お守り」「健康管理」など、ポジティブな理由を添えて渡す
- 慣れるまで家族も一緒に使って見せる
- 「みんなも安心できるから」と家族の気持ちを伝える
最初は戸惑いや抵抗があっても時間をかけて少しずつ慣れてもらうことで、きっと良いパートナーになってくれるはずです。また、どうしても身につけることに抵抗してしまう場合やご本人が装着や充電などを行えない場合には、衣服や靴に目立たず装着できるタグ型や薄型のGPS機器を選ぶのもひとつの方法です。
こうしたGPS機器の活用に加えて、地域のサポート体制についても知っておくと、より安心です。
高齢者の徘徊「相談先と地域で使える支援サービス」を知っておこう
徘徊に限らず、介護に関わる不安や悩みはひとりで抱え込まず、地域のサポートを活用しましょう。
まずはじめに相談
地域包括支援センター
お住まいの地域にある、高齢者の総合相談窓口です。ケアマネジャーの紹介や、高齢者向けサービスの情報も教えてもらえます。
市区町村の介護保険課
介護保険の手続きはもちろん、地域の見守りネットワークや認知症カフェの情報なども。
地域で受けられる支援
見守りネットワーク
郵便配達の方や新聞配達の方、近所の商店の方々が、日常の中でさりげなく見守ってくれる仕組みです。多くの自治体で整備されています。
認知症カフェ
同じ悩みを持つご家族と出会える貴重な場所です。「一人じゃない」と実感できる、心の支えになってくれるでしょう。
家族と本人が安心して暮らせる環境づくりを
認知症による徘徊は、ご家族にとって大きな心配のひとつです。けれど、日頃の小さな備えに加え、GPS機器などの技術や地域とのつながりを活かせば、ご本人らしい暮らしを大切にしながら見守ることができます。できることから少しずつ始めていきましょう。